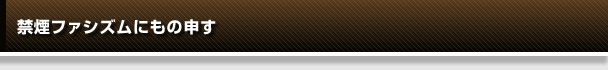禁煙ファシズムにもの申す
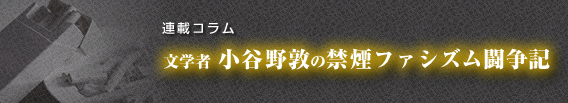
最近、敷地内を禁煙にしてしまう病院が増えている。実に困ったことだ。 病院なのだから当然だと思う人もいるだろうが、実はそうではない。病院こそ、喫煙の場を確保しておくべき場所なのだ。 大きな病院へ行くとき、人は不安を抱えている。もしかすると、既に何かたいへんな病気を告げられて、大きな病院へ来たのかもしれないし、まだ分からないで来るのかもしれない。そして、もしかするとそこで、大きな病気を告げられたり、その治療が困難であると知らされたりするのだ。 喫煙の習慣がない人は関係ないだろうが、喫煙者にとって、そこで受けた打撃は、喫煙によって、とりあえず癒したいものだ。だが、敷地内禁煙などという病院は、そうした精神のひとときの癒しすら、患者から奪うのだ。何という、人間の心を理解しない、冷酷な仕打ちだろう。 いやもちろん、医師とは昔からそのようなものだ、と盛んに言われている。どうやって厚生(労働)省の覚えをめでたくするか、患者のことより自分の金儲けのことばかり考えているのが医者だと、みなが口を揃えて言うくらいだ。 だが、この、敷地内全面禁煙というのが、いかに非情か、たとえば精神科医であれば分からないはずはない。精神科の入院病棟では、さすがに喫煙は許されていると聞くが、実情はどうだか分からない。都内の大病院として知られる慶応大学附属病院では、病院の庭に喫煙所があり、点滴の機械を引きずってそこまで吸いにくる入院患者が何人もいる。何という冷酷な仕打ちだろう。しかしこれも、冷酷非情な厚生労働省の指導によるものだ。 たとえば、肺気腫のような、これ以上吸うことが命に関わるというような病気なら、すぐ禁煙してくれ、というのも当然だ。だが、たとえば肺がんの患者が、もしこれまで喫煙していたとして、そこで突然タバコをやめたからといって、その後にはほとんど影響しない。一時期、肺がんでもすぐにやめればその後の経過がいい、などと言いだした医師たちがいたが、嘘である。 病院だから全面禁煙はしょうがないと思う人がいるとしたら、それは間違いだ。それは単なるイメージに過ぎない。 やはり国会図書館並みのきちんとした喫煙所を設けるのが、正しい仁術の道である。かつて、作家の澤野久雄が、肺がんを宣告されて、タバコを吸っていたら看護婦が注意したので、「どうせ死ぬんだから吸わせてくれ」と言ったら、看護婦の顔色が変わったという。 顔色が変わったのは、「どうせ死ぬ」の語に衝撃を受けたからだろう。しかしいずれにせよ、吸い続けるかやめるかで、肺がんのその後に大した影響はない。 大病院の中には、明らかに元は喫煙の場所だったと分かるスペースのあるものがある。そこは今では誰も入れず、ちょっとばかり廃墟じみてきている。それは、ひたすら、人間の愚かさを現していた。日本医師会や国立がんセンターは、タバコを目の仇にしているようだが、人は誰でも必ず死ぬのと同じように、人は誰でも長生きできるわけではない。 司馬遼太郎は、『世に棲む日々』で、若くして刑死する吉田松陰を描いて、どんな短い生涯でも、人の生には春夏秋冬がある、と書いた。医師会やら、「脱たばこ社会」などを提言した日本学術会議の連中に、こんな哲学はまったく欠けていると言うほかない。 小谷野敦:東京大学非常勤講師 比較文学者 学術博士(東大) 評論家 禁煙ファシズムと戦う会代表 |
| 2007.07.30 |