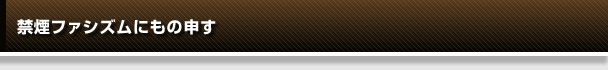禁煙ファシズムにもの申す
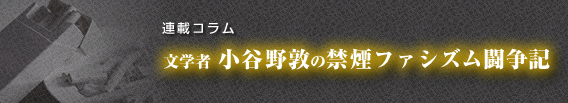
私は最近、さんざん毎日新聞の記事を叩いているが、それは毎日新聞をとっているからで、というのは毎日がいちばん禁煙ファシズムが緩いからで、それでもこれだけ禁煙ファシズム記事はあるのだ。多分読売や朝日はもっとひどいので、決して毎日に恨みがあるわけではない。 その毎日の二面左下の記者による囲み記事は、禁煙ファシズム記事が載ることが多いが、先日、いい記事があった。報道部の大島透によるものだ(7月22日)。 大島は、連載「がんを知る」での、中川恵一・東大附属病院准教授による、今の日本人は、永遠に生きられるよな「死なない感覚」があるのではないかという言葉を紹介している。 大島は、先日、がんで死去された父上の臨終に立ち合ったと書き、言う。「誰しも生まれた時から死ぬことはすでに決まっている。地球上のあらゆる生物で過去に死ななかった者は存在しない。死はそれほど自然な現象だから、身構える必要はない。そう思うと、不思議に元気がわいてきた」。 中川は、がん治療を専門とし、特に緩和ケアを重視する医師だ。緩和ケアは、要するに、どれほど苦しまずに死ねるかという技術である。日本ではまだ緩和ケアへの理解が不十分で、多くのがん患者は、それでは死ぬのを待つようなものだというので、「治る」ことを求めるし、医師も、この緩和ケアを軽視してきた。しかし、治療不可能な病気がある以上、緩和ケアは避けて通れない問題だ。 さて、現在の「禁煙ファシズム」の背後に大きく広がっているのは、この「死なない感覚」だろう。健康に留意しさえすれば、たばこや酒を控えれば、永遠に生きられるような感覚。それは、言ってしまえば、病んだ感覚であり、古代の皇帝が抱いたような永遠の生に関する妄想だ。 最近ベストセラーとなった「健康本」に、たばこを吸いながら90歳まで生きた人もいる、という意見に対して、吸わなかったら100歳まで生きただろう、とあった。なんという愚かさだろう。 人類史上、現代の先進国の人間はかつてない量の情報にさらされている。その結果、小児的な全能感が、ある側面において人々を襲い、それが「死なない感覚」を生んでいるのだ。 宗教学者の山折哲雄は、昨年はじめ、子供たちに「生きる力」を与えようといったキャンペーンは、「死を避ける」ものであり、現代では高齢化によって実際には死は身近なものになっているのに、人々の意識の中では、死とはかえって遠く、死を遠ざけようとしているのではないかと述べていた。 卓見である(「北海道新聞」06年1月30日など)。見出しには「死生観忘れた生の合唱」とあり、山折は、「共生」とよく言うが、それには「共死」もつきものではないかと言っている。 前回私は、なぜ医師たちが、こうもタバコを目の敵にするのか、と書いた。恐らく彼ら、特に内科医は、連日、多くの患者の死を看取っているのだろう。それは私のような一般人からは想像もできない、まるで死刑執行人のような役割だ。 末期がん患者で、「私がどんな悪いことをしたっていうんです」と泣きながら医師に食って掛かる人もいるという。 高齢化社会で、八十くらいまで生きるのが当然のように思われている時代に、六十代、七十代はじめでがんで死んでいく人々は、昔なら寿命で済んだ年齢なのに、まるで若死にでもするような気がするのだろう。そうした人々を見続ければ、医師の中には、潜在的に精神を病み、禁煙ファシストと化す人が出てくる。 私は、禁煙ファシスト医師らを見下し、揶揄して言っているのではなく、先進国の国民の中の、永遠に生きられるかのような意識が、こうした医師たちを苦しめているのだと思う。 先日、日野原重明の文庫『長さではない命の豊かさ』(朝日文庫)が出た。元本を改題したものだが、この改題は歓迎したい。日野原は、自身がたまたま長命を保ったために、生活習慣病という語を広め、あたかも生活習慣さえ改善すれば日野原のように長生きできるかのような幻想、とにかく長生きすることがよいとするかのごとき意識を広めた点で罪なしとしないからだ。 文明が進歩すれば、誰もが九十、百まで生きられると幻想するのは、近代がもたらした悪の一つである。 「ポストモダン」などと言ってみても、そうした意識はモダン真っ只中だと言うべきだろう。この意識を乗り越えた時、先進国の国民は、近代の悪の一つを超えた新たな成熟にいたるはずだ。 小谷野敦:東京大学非常勤講師 比較文学者 学術博士(東大) 評論家 禁煙ファシズムと戦う会代表 |
| 2007.08.30 |