禁煙ファシズムにもの申す
戦争と女の顔 |
R
監督はロシアの新鋭カンテミール・バラーゴフ。主演女優2名も無名の新人。
ナチスドイツのバルバロッサ作戦によるソ連奇襲で緒戦に大敗、膨大な数の戦闘部隊が壊滅してモスクワ陥落の瀬戸際まで追い詰められた独裁者スターリンは、本来は銃後の役割の女性を数百万人もソ連軍に動員してナチスドイツ軍と戦わせた。彼女達の中には戦闘機パイロットや狙撃兵、砲兵、パルチザンとして最前線で勇敢に戦った人もいたが、大半は最前線の戦闘部隊ではなく衛生兵、輜重兵などだった。ソ連軍は独ソ戦で約1400万人が戦死したというが、女性兵士の戦死も数知れなかった。彼女らの貢献がなければ、ソ連の勝利は無かったわけだ。
しかし戦後、ソ連の郷里に「英雄」として復員した女性兵士を視る世間の風は冷たかった。 映画を観た感想は重苦しいものだった。決して楽しい作品ではなく、考えさせる作品だった。
主人公は身長180センチ以上あろうかという痩身の大女。PTSD(心的外傷後ストレス障害)を抱えていて、時々心身硬直する。余談だが、ロシア映画だが、主演女優は名前のミロシニチェンコからするとウクライナかベラルーシ系だろう。演技は淡々としているが凄みのある存在感がある。 主人公は戦友の女性復員兵が戦場で産んだ男児を預かって養育している。その男児をPTSDの発作で窒息死させてしまったことを巡って、戦友の女性復員兵との間で引き起こす様々な葛藤と、当時の共産主義圧政下のソ連社会の男女の唯物論的な性関係を赤裸々に描いていく。 愛煙家として強烈に記憶に焼き付いたのが「末期の煙草」の場面。 映画を通じて何を訴えたいかという視点からいえば失敗作だろう。余りにも視野が狭く、原作のごく一部を切り取っただけの題材のみにこだわり過ぎて広範な視点が乏しいからだ。 しかし、日本のお花畑的な世界観にどっぷり浸って、何ら疑問を感じない人たちには、ぜひ観て考えて欲しい作品だ。「戦争は嫌だ」と何か呪文のように唱えていれば、本当に戦争がなくなると盲信して現実逃避している人たちは、世界の現実の凄まじい重さを実感できるだろう。
現在、ロシアのウクライナ侵攻で、ウクライナは焦土となっている。ロシアは完全な加害者の立場だ。この映画の監督バラーゴフはおそらくプーチン政権下で迫害を受けていると思われる。原作者のアレクシェーヴィッチはロシアの同盟国の母国ベラルーシから逃れてドイツに事実上の亡命生活を送っているという。ウクライナ戦争は長期化が予想されているが、いずれは終わる。その後にこの監督が加害者としてのロシアをどう描くかで、真価が分かる。 公式サイト |
| 2022.06.22 |


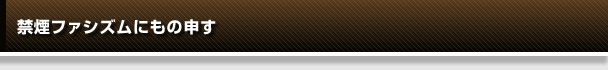
 2016年にノーベル文学賞を受賞したベラルーシの閨秀作家・ジャーナリストのスヴェトラーナ・アレクシェーヴィッチの処女作「戦争は女の顔をしていない」を原案とした2019年のロシア映画である。同年のカンヌ映画祭の「ある視点」部門で国際映画批評家連盟賞と監督賞、他にトロント映画祭など世界各国で30もの映画賞を受賞し、ロシア国内でもゴールデンイーグル賞と主演女優賞を獲得した話題作だ。
2016年にノーベル文学賞を受賞したベラルーシの閨秀作家・ジャーナリストのスヴェトラーナ・アレクシェーヴィッチの処女作「戦争は女の顔をしていない」を原案とした2019年のロシア映画である。同年のカンヌ映画祭の「ある視点」部門で国際映画批評家連盟賞と監督賞、他にトロント映画祭など世界各国で30もの映画賞を受賞し、ロシア国内でもゴールデンイーグル賞と主演女優賞を獲得した話題作だ。