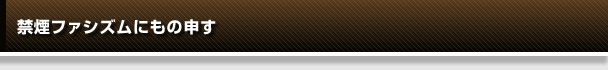禁煙ファシズムにもの申す
| 禁煙ファシスト松沢成文(2) |
私は、幕末、明治期の日本の知識人たちが、西洋文明の優れていることを知り、それを移植すべく実にすばやい努力をした、というようなことを、小説やドラマで目にすると、祖先たちの知性に対して目頭が熱くなるほどのナショナリストである。しかし、ではそれ以後のことはどうかというと、何も、西洋に学ぶことはもはやない、とまでは言わないが、幕末明治期のように、科学技術や議会制度などを移入した時代とはまったく違う状態であり、独自の取捨選択をすべきものであるのは当たり前のことであり、世界の潮流であれば正しいなどと考えるのは、自ら考える頭を持たない者の言うこと、あるいは大勢に従えば無事安穏と考える卑怯者の言うことである。 たとえば、パリではカフェまで禁煙になったと報道されているが、カフェにはテラス席というものがあってそこは喫煙可なのであり、西洋諸国は、屋外での喫煙に対してさほど厳しい措置をとってはいない。路上喫煙に課金とか、駅のプラットフォーム禁煙とか、大学のキャンパス禁煙とか、屋外での禁煙は日本の特徴である。 というのは、西洋では自動車の害に対しても、都市部への乗り入れの制限などを行っているからで、しかるに日本では、飲酒運転への厳罰化は行われたが、自動車の運行制限には至っておらず、却って緩くなっているくらいだ。禁煙ファシズムは世界的(西洋中心の)であっても、日本の場合、「酒と自動車に甘い」という点が甚だしくおかしい また「毎日新聞」だが、数ヶ月前に全面記事で野田聖子をとりあげ、野田が「酒豪」だと「持ち上げ」、「酒豪の総理、いいかもなあ」などと結んでいたが、間には、野田が泥酔してトイレで倒れたなどという話まで出てきた。飲酒に厳しい西洋では、そんな人物を首相になどと書く記者はいまい。赤塚不二夫が死んだ時も、各メディアは「病気でも酒を手放さなかった」などとまるで偉いことのように書くのだが、筑紫哲也が肺がんになれば、煙草のせいだと責め立てるのはどういうわけか。 「肺がんでも煙草はやめなかった」などと称揚する新聞はあるまい。おかしな二重基準である。大酒は喫煙同様体に悪いに決まっているし、自動車は排気ガスと事故で他人を害するものであり、遊びでのドライブなど規制するのでなければ筋が通らない。 松沢もまた、自動車については、排気ガスの毒性を弱める程度のことしか言わないのだが、いっそ神奈川県内では必要不可欠な場合以外の自動車の使用を禁じるのでなければ、整合性がないだろう。むろん、飲食店の全面禁煙が、経済に打撃を与えることくらい、承知の上なのだろうから。 今ではありとあらゆる新聞が「酒と自動車に甘い」「日本独自の」禁煙ファシズムに加担しているが、このところの、米国発の社会政策は、概して清教徒的になってきている。そして、世界中がこの方向へ行けば、「外部」がなくなって、たとえばソ連の独裁に抵抗して亡命するというような選択肢すらなくなるわけである。 知事というのは、地方行政体の首長であり、地方分権によって独自の施策を行う裁量権が認められている。これは、中央権力が全権を掌握するような、「外部」のない世界を作らないようにする知恵である。ところがその知事本人が、世界の潮流に遅れないように、と言ったのでは、要するにもしあらゆる都道府県知事がそのように考えたら、日本中どこでも同じ条例ができることになって、多様性も、地方自治の精神も失われるのである。 もしどこかの県知事が、自分の県では路上喫煙での課金などは許さないという条例を作ったら、それは独自の施策になるが、松沢のやり方は、単にいま進行しているものを自分の県ではもっとひどくしようとしているだけであって、知事というものが「世界の潮流に乗り遅れないように」と考えることは、地方自治体の長として、地域の独自性を否定する、自己の存在理由を失わしめる発想にほかならないのである。むしろ「世界の潮流だからといって従わなければならない理由はない。わが県は独自にものを考える」というのが、地方自治の精神ではないのか。 いじめ論議も近年盛んだが、いじめというのはしばしば、他と違う者、他の者たちの流儀に従わない者に対して行われるもので、リベラル派の教育学者たちは、多様な個性を認める教育をなどと言っているが、松沢の発想はまったくその逆、大勢の流儀に従うべきであり、従わない者はいじめるぞ、という「いじめっ子」側の発想なのである。 もちろんそれは松沢には限らない、禁煙推進議員連盟(会長・綿貫民輔)とか、日本禁煙学会(会長・作田学)とか、禁煙運動家らのNPOもみな、いじめっ子精神の持ち主なのである。一九七〇−九〇年代に嫌煙権を主張することと、いま主張することとは、まったく意味が違う。昨日の反体制勢力は、今日の体制勢力になるのである。 あるいは、今年は売春防止法の施行五十年に当たる。明治以来、西洋諸国とともに、日本の知識人たちは売春廃止のため営々たる努力を続け、五十年前、これで売春はなくなると多くの人が信じたが、それはなくならず、さまざまな形態で残っている。既に三十年も前に詩人の関根弘は、売春防止法に賛成したことを反省している。私もまたかつて売春の徹底根絶を唱えていたが、既にドイツ、オランダなどでは売春は合法化されている。喫煙は滅び行く文化だと言う人もいるが、恐らく喫煙は売春と同じように、滅びることはないだろう。 この世の中から一切の悪、不健康などを排除しようという考えは、フランス革命の大虐殺や、スターリンやポル・ポトによる粛清を生んだのである。私は廃娼運動家たちの善意を疑わないが、善意から始まったものが悲惨な結果をしばしば生んだというのは、哲学者カール・ポパーの説くところである。 ところで、また日本人の平均寿命が伸びたが、禁煙政策に成功したと豪語する米国の平均寿命が日本より遥かに低いのはどういうわけだろうか。寿命を決定するのは社会的格差だという説は、ここから見ればかなりの説得力を持つはずで、松沢の言うように日本が世界の潮流に遅れているとすれば、どうして平均寿命が伸びるのだろう。 要するに喫煙と寿命の間にさしたる関係はないということだ。もっとも今や禁煙ファシズムは、そんな統計やら疫学の問題ではなくなってしまった。単に「過ぎたるは尚及ばざるが如し」という簡明な倫理の問題でしかなくなっている。今や、わがままの限りを尽くしているのは、禁煙運動家どもなのである。 小谷野敦:東京大学非常勤講師 比較文学者 学術博士(東大) 評論家 禁煙ファシズムと戦う会代表 |
| 2008/11/04 |