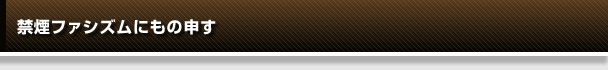禁煙ファシズムにもの申す
| 郡山遠征記 その3 |
小谷野 敦
しかし喫煙環境は、首都圏と変わらずひどかった。 私は文学館の、ガレージのようなところで、暑い中、吸わなければならなかった。 禁煙ファシズムがひどいのは、首都圏とか大都市部だけで、田舎はまだのどかなものなのだろうと思っていたが、そうでもなかったのである。 どうやら、国立の施設はまだ喫煙室などがあるが、公立つまり地方自治体関係のものが特にひどいらしい。 ねじ込む嫌煙・禁煙運動家がいて、あっさり屈してしまうからだろう。 山村氏は、「私はねえ、この四月からなんですよ、その前は学校の校長していて、文学のことなんかなーんにも知らなかったです」と言う。 小学校で音楽の先生をしていたというので、私は灰皿の脇に坐り込みながら、今はどんな歌を歌うんですか、などと訊いていて、ふと、中学時代の音楽の教科書に、ノビコフの「二人の兵士」とかいう歌があって、それが結構好きだったことをふと思い出した。 後で調べたら「ある兵士の話」だったが、恐らく「大祖国戦争」つまり第二次大戦でのドイツとの戦いを描いたもので、最後は勝利に終るのだが、いかにも日教組支配する当時の中学校らしいものだったな、と思った。 しかし山村氏は、館長になってからあれこれ読んで、大正文士の生活ってのは面白いもんだなあと思いました、と言っていた。 十二時近くなり、講演は一時半からなので、山村氏の自動車で中華料理店へ行き、冷し中華を食べた。 私は、禁煙の店は困りますよと言ったら、山村氏は、いやー、なかなか難しいですねなどと言っていたがちゃんと喫煙可であった。 自動車に乗り込んだら、暑い中に置いておかれたから蒸し焼きになりそうで、すぐ冷房を入れて窓を開けてもらった。車内で山村氏に名刺を渡した。 私の名刺は、かつては「東大非常勤講師」「日本文藝家協会会員」「国際日本文化研究センター客員助教授」が並んでいたが、東大をクビになってから、そこを「禁煙ファシズムと戦う会代表」にしていた。 山村氏は、それを見て、「センセ、私この、この肩書については紹介いたしませんので、まあどうか、そのことは、お話の中で……」とまた神経質になっているようなので、いやいや、紹介なんて、簡単でいいですよ、時間がもったいないし、と言った。 実際、久米正雄伝の初稿を書き終えたばかりの私には、話すことが多く、これは一時間半では収まらないなあ、と思っていて、結局『破船』事件を中心にするしかないかと考えていたところだったのである。 会場となっている市民文化会館のようなところへ着いて、エレベーターで五階まで上がり、待合室へ案内された。 会議室だったが、やはり禁煙だったし、まだ三十分もあったから、山村氏に、吸えるところは、と訊くと、一階まで降りて、横手から出たところ、屋外に、灰皿があった。 いやあ、こんな大きな建物でも一つも喫煙室がないんだなあ、これが猛暑の日で、熱射病にでもなったら、禁煙ファシズムに殺されたってところだな、と思いつつ、そこで吸っていた。 若い男女が、やはりそこへ吸いに来ていて、吸っているのは男のほうだったが、屈託がなかった。 私も、もしこれくらいの年齢だったら、むしろ煙草をやめていたかもしれない。 逆に、もう少し上の三十代だったら、一番辛かったかもしれない。 今の私は、禁煙の会議に出る必要もないし、東北への出張を命ぜられることもない。 大学の先生で、飛行機が禁煙になってから、外国へ行けなくなってしまった人もいる。 私は、東大をクビになって以来、大学への恨み言を言うような著書をいくつか出したし、その間も、大学教授になれないことが悔しくて、歯ぎしりをするほどだったが、その五月から六月にかけて、どこの大学からも、教授になってくれとか非常勤をやってくれとかいう話がなく、何だか面倒で、もういいや、と諦めの境地に達しつつあった。 もっとも、また何かがきっかけで執着が芽生えるかもしれないけれど。 一時二十二分になったので、そろそろ行くかと、五階まで上がると、月山さんが、待合室でお待ち下さい、と言う。 禁煙の待合室になど、坐るだけでも汚らわしいと思ったが、まあしょうがねえやと入って坐ると、正面に、草書体の書が掛かっていて、読めなかったので、脇に坐っていた山村氏に、あれは何て読むんでしょうねえと言ったら、そばまで行って「水中禅、と書いてあります」と、説明文を読んだ。 「誰の書ですか」と訊いたら「青山……すぎ、あめ、とありますが……」「ああ、青山杉雨(さんう)ですね」「えっ、これで『さん』って読むんですか」「そうです。藝術院会員ですよ」「いやあ」とこちらへ戻って来ながら山村氏は、「杉花粉症なんで杉には弱くて」と言っていた。 山村氏は、最初に挨拶をするので緊張していたわけでもあるまいが、私の紹介文を見て、「センセ、この『聖母のいない国』というのは、これは、マドンナ、とお読みするんでしょうか」 と言う。 そんなことを訊かれたのは初めてである。いえいえ、せいぼ、でいいんですと言ったが、火曜サスペンス劇場の主題歌「聖母(マドンナ)たちのララバイ」を岩崎宏美が歌ってヒットしたのは一九八二年、私が大学に入った年で、山村氏が六十一だとすると当時三十四歳か……。 それから、あまり聴衆が集まっていない、というようなことを、申し訳なさそうに言うから、まあ久米正雄ならそうだろうと思い、私はカナダ留学中に講演を頼まれて、行ったら一人も来なかったこと、ありましたよ、まああの時は悲憤慷慨しましたが、そういうことも、慣れてきますねなどと言った。 「五、六人ですか」 「いえいえ、五、六十人で……。なんか文学講座みたいになって」 「ああ、それだけいりゃあ御の字ですよ」 ふっと時計を見ると、もう一時三十二分になっていたから、ああ、時間じゃないですかと言って、二人で室へ急いだ。 入ると、まあまあの入りだったが、どうやら大きい室を、入場者が少ないので途中に間仕切りを設けたらしかった。 後ろ左手から入り、私は左手へ回ろうとしたら、先生こっちですと言われて右手へ回り、正面上手に、何やら審査員のように山村氏と坐った。 妙に悠長だなあと思ったが、山村氏はおもむろに中央へ進み出ると、「えー、平素より、郡山文学館に暖かいご支援を賜りお礼申し上げます。わがこおりやま文学の森は平成、十二年に開館いたしまして、鎌倉、二階堂にありました、久米、正雄邸を移築いたし」と、こんな風にぷつぷつ切りながら話し始めた。 「さて、今回は、久米、正雄展開催に伴いまして、特別企画として、おさの先生に来ていただき、久米、正雄と文学、という題で、特別講演をして、いただくことになりました」 ありゃりゃ、と思ったが、最初はいくぶんくぐもった「おさの」だったが、二度目からはもうはっきり「おさの、とん先生は」と始まった。「東京大学英文科卒業、同、大学院、比較文学、比較、文化博士、課程、修了」と妙なところで切るのである。 「大阪大学、言語文化、ハン」と言ったように記憶するのだが、少なくとも「部」と言わなかったのは確かである。「国際、日本文化、研究センター」のあと「客演、助教授」と言ったように聞えたのは、イとエが混淆する訛りだったかもしれない。私は脇で笑いを堪えていた。 あとから登壇して、「ただ今、おさのと紹介されました小谷野です。まあ、間違いというものはあるもので、私も今まで、おやのとかこたにのとかおのやとか、いろいろ呼ばれてまいりました」 と切り出したが、だいたいパンフレットにも、会場入り口の看板でも私の名前にはルビが振ってあるのだから、気づいている聴衆もいて、みなくすくす笑っていた。 ほとんど老人だったが、老人相手の講演はやりやすい。「有島武郎は、森雅之のお父さんですね」とか、久米正雄の一人息子の昭二さんは「お笑い三人組」のディレクターで、といったネタが使えるからで、機嫌よく一時間半話し、きっちり三時に終えた。 すると、どういうわけか花束贈呈というのがあって、月山さんがでっかい花束を渡してくれたが、たとえ東京都内で講演をしても、井の頭線に持ち込めないくらい大きかったから、宅急便で送ってもらった。 しかし、もう再び五時間使って帰るのは無理だと思った。 山村氏に駅まで送ってもらった私は、ちょうど来た新幹線に飛び乗ると、JR東日本を呪詛し、身動きをしたりすると吸いたくなるし恐怖の発作が起きる気がしたので、じっと身を潜めるようにして、一時間半を、大宮まで耐えたのである。 大宮駅で降りて、これまた遠いところにある喫煙室に飛び込んだが、二度と東北方面へは行かぬ、この新幹線に喫煙車両が出来るまで、と思ったのであった。 〈終わり〉 小谷野敦:比較文学者 |
| 2010/09/22 |