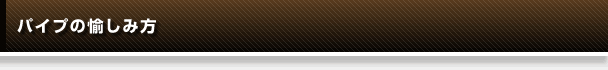パイプの愉しみ方
『50にして煙を知る』第1回
およそ、この世でもっとも苦手なものはタバコの煙である。100メートル先の他人の歩きタバコの煙で、頭が痛くなるほどである。これはいまでも変わらない。
そんな私に去年、「煙を吸え」と勧めた御仁がいた。日経新聞の平野憲一郎氏である。
ある会合で初めて親しくお話する機会を得たが、その時「どこかでお会いしたことがあるな」と、ぼんやりとした記憶をたぐりよせることができたのは、彼がパイプをくわえていたからである。
思い出した!
私も現役の政治記者だったから平成以前、たぶん昭和末期だろう。
衆議院の社会党記者クラブで、いつも悠然とパイプの煙をくゆらせながら原稿を書いていた新聞記者がいた。
当時はパソコンやワープロなどという神経をいらだたせる機器もない。執筆は原稿用紙にエンピツでぐいぐい書き込むきわめて人間臭くエネルギッシュな作業である。彼にはパイプと鉛筆が実によくマッチしていた。それが若き日の平野氏である。
彼の個性も強烈だったが、それ以上に鮮烈だったのは、あのパイプを手にしていた鬼気迫る横顔であった。
再会の宴が進むにつれ、当時同様、鋭い眼力を発揮した氏は、私のしょぼい姿を覗き込んでこう託宣した。
「あなた、人生に相当疲れているね。気分転換もあまりうまくなさそうだ。私のようにパイプを吸ったらどうか」
氏の状況判断はまったく正しい。
3年前から大学教員になり、自分の子供とほぼ同年齢の学生に、決まりきった講義を延々と続ける日々は、記者という刺激的な職業に比べると、えらくストレスがたまる。しかもそれを跳ね返す若さはもうなくなりつつあった。
たぶん生気のない幽霊みたいな表情をしていたのだろう。
巻きタバコの臭いは勘弁してほしいが、氏のパイプから出てくる煙はなんともいい香りがしていたのも事実で、断る理由もなかった。
「50にして天命を知る」というが、こうして私は「50にして煙を知った」人間となった。
ところが、前述したように、これまで喫煙の習慣は皆無。ニコチンの味も、ライターやマッチで火をつける動作すらやったことがない。ましてやパイプはどんなものがいいのか、どこで買ったらいいのか、どうやって扱うかもまったく知らない。
「そう言われてもなあ…」―私の心を見透かしたように氏は言った。「日本パイプスモーカーズクラブに来なさい。月に一回、銀座で愛好家が集まってパイプを楽しんでいる。吸う、吸わないは問わないから、一度顔を出せばいい。おおらかな人間関係だけで、あなたのストレス緩和になる」
もう来るのは当然だ、といわんばかり氏の一言で、私はおそるおそるクラブに出かけていくことになった。
うゎあー、本当だ。老若男女20数名の方がゆったりと集っている。こんなにパイプ姿が並んでいるのは、一種壮観でもある。
偶然だが、その日は年2回クラブ主催のパイプ・オークションが行われる日であった。
私は市場価格よりも遥かに安価で数本のパイプ、関連道具一式を購入できる僥倖にも恵まれた。
かくして、私のパイプ人生は52歳からスタートした。