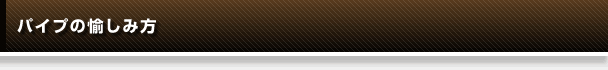パイプの愉しみ方
『50にして煙を知る』第30回 SMOKABLE永田町3〜花岡信昭さんの人生作法
夏、それは戦後のわが国にとって鎮魂の季節であり、お盆では新たに逝った人々の不在に、深い喪失感を覚える――。
最近、そういう気持ちが顕著になったのは、私自身が「人生の折り返し地点を大きく過ぎた」という実感があるからなのだろう。
拓殖大学大学院教授・花岡信昭さん。この5月に65歳で、早すぎる天国への旅に立った彼は、私にとっては大学院時代の敬愛する恩師であるが、ジャーナリズムの世界では元産経新聞政治部長、保守の論客といったほうが、はるかに通りがいい。
本欄で取り上げる価値は、充分すぎるほどある。彼は40年以上にわたる筋金入りのスモーカーであり、タバコに対しても、人生に対しても実に折り目正しく向き合った人物だったからだ。
恩師のタバコ
初めてお会いしたのは、9年前。意を決して48歳で大学院修士課程の門を叩き、親子ほど違う年齢差の学生と机を並べた時だ。地方行政学、アメリカ宗教政治特論、南西アジア史英文文献購読など、週に9コマもの履修数には閉口した。
法学部出身なので、政治学となると、余分に取得する科目も上積みされるからだ。仕事を抱えながら、四半世紀ぶりのキャンパスライフはさすがに楽ではなかったが、必要に迫られて通うことを決めたのだから、泣き言も言えなかった。
土曜日午前の「政治学」担当教員が花岡さんだった。この講義だけは他とはいささか趣きが異なった。当時の彼の肩書きは産経新聞・論説副委員長。
小泉内閣時代でもあり、政治もなかなか面白い季節で、受講生に新聞記事や選挙情勢など、政界関係者でないと読み慣れない資料を配布しながら、政局の行方を推し測る作業である。
「まず通常国会の後半日程だ。サミットもあるし、あんまり引っ張れないな。そうなると秋の臨時国会に向けて重要法案の駆け引きは……」と、花岡さんが玄人筋の解説と政治家の心理を解き明かしながら、ホワイトボードも使って問いかける。
私、そして本欄にたびたび登場する丹羽文生氏(当時22歳)がおのずと中心になって、質問をテニスボールのように打ち返す。そんな「頭の体操」をやっていると、すぐ昼になってしまう。
 終わると講師控え室で、花岡さんは、実にうまそうにゆっくりとマイルドセブンを一本吸い尽くす。文字通り、吸い尽くすのだ。
終わると講師控え室で、花岡さんは、実にうまそうにゆっくりとマイルドセブンを一本吸い尽くす。文字通り、吸い尽くすのだ。
それはシガレットを覚えたての連中がカッコつけてくわえ、片手に缶コーヒーを持ち、半分も吸わないうちに消すなどという、葉タバコ生産者に失礼な態度とはほど遠い姿だった。
毎日マイルドセブン1箱から1箱半が、彼のペースだったが、深く吸い込み、煙をくゆらせ、フィルター近くまで律儀に吸う。それはそれは真摯な作業で、この儀式を終えると、ランチタイムとなる。
新聞記者の世界では、昼食程度なら年長者が面倒を見るという暗黙の掟どおり、われわれは、土曜日の昼は毎回彼にご馳走になっていた。学内食堂も、近所の店も禁煙だったから、こういうパターンにならざるを得ない。
「タバコは記者の俺には絶対に必要だ」との信念は、吸わない私にも痛快だったが、酒が一滴も飲めないのは不思議だった。
文章とカラオケ演歌のうまさは際立っていた。学生には「いいか、まず書いてみろ。文章を書くことは恥をかくことだ。いま書いたものが、現時点での己の実力。それを伸ばすには、毎日新聞や本を読むことと、文章を書くことしかないんだ。学生時代に大いに恥をかいておけよ」が決まり文句。
小生のような年長者で、同じ世界の片隅にいたものには、ちょっと違うアドバイスだ。「物書きならば、オファーがあれば、どこから来ても書かないといけない。思想が違うから書けないなんてのは、プロじゃあない。相手の立ち位置を考え、自分の主張を盛り込むことはいくらでもできる。それでメシを食うんだから」―-うーん、参った。このコラムを書き始めたのは、彼の教えが頭をよぎったことも否定しない。
実際、多くの連載を抱え、「毎日が締切日なんだ」とぼやきながら、深夜になると本人曰く「鬼神が乗り移ったがごとく」頭が冴え、あらゆる種類の原稿を書き続けていた。そのまま大学の講義、講演にも行き、自らにそれを課すことを楽しんでもいた。そうして得た原稿料で、僕らによくご馳走してくれ、社会還元を果たしていた。
硬骨漢逝く
 昭和21年生まれの彼は「大手新聞社で初の戦後生まれの政治部長」という名誉な記録も持っている。
昭和21年生まれの彼は「大手新聞社で初の戦後生まれの政治部長」という名誉な記録も持っている。
新聞社も役人の世界と同じで、政治部長ならば同期の政治部記者から一人しか出ないのが掟(慣例)だ。腕だけよくても部長にはなれない。「腕がいいのは当たり前だ。部下への気働きができなきゃ部長にはなれんよ」とよく語っていたが、実はもっと大事なことは、どこの世界でも同じだが「上への覚えがめでたいこと」だ。
花岡さんは名立たる硬骨漢で、それをせずに部長になった稀有な例と聞いているが、それは本人、一言も言わなかった。
長野県出身の花岡さんは、田中康夫氏の同県知事再選を阻止せんがため、突如、社を辞して一時、出馬を表明したのには驚いた。
そのとき、政界、言論界あまたの大物はもちろん、社をまたいで団塊の世代の記者仲間が、資金集めに協力し、大学院の教え子が数人、「一大事です。長野に行きます」とボランティアで選挙運動に馳せ参じた。
花岡さんがいかに慕われ、尊敬されていたか、その人間力を見せ付けられた思いだった。
タバコに関しても一家言持っていた。
錚々たる執筆メンバーで昨年出版された「愛煙家通信」(喫煙文化研究会編)に「たばこのみ狙い撃つ“空気”への大いなる違和感」なる一文を寄せている。最後のフレーズは、花岡節の面目躍如たるものがあるので引用する。
 「雨、雨、ふれふれ」で有名な八代亜紀のヒット曲「雨の慕情」(阿久悠作詞)は、長い月日の膝枕で膝が別れた恋人の重さを覚えているとし、「たばこをプカリとふかしていた」という一節がある。このほんわかしたシーンに隠された泣きたくなるほどの情念。これが人間の人間らしいところなのだが、禁煙・嫌煙ファッショが世を覆うようになれば、こうした情念もどこかに押しやられ、やがて消え去ってしまうのだろう。
「雨、雨、ふれふれ」で有名な八代亜紀のヒット曲「雨の慕情」(阿久悠作詞)は、長い月日の膝枕で膝が別れた恋人の重さを覚えているとし、「たばこをプカリとふかしていた」という一節がある。このほんわかしたシーンに隠された泣きたくなるほどの情念。これが人間の人間らしいところなのだが、禁煙・嫌煙ファッショが世を覆うようになれば、こうした情念もどこかに押しやられ、やがて消え去ってしまうのだろう。
私のパソコンには5月10日で途絶えた花岡さんの最後のメルマガが遺されている。民主党には終始きつい注文をつけていたが、葬儀には森元総理など自民党大物政治家はもちろん、岡田克也・幹事長らの民主党政治家の顔も多くあった。
同党には厳しかったが、個人的に会っては的確なアドバイスもしていたのだろう。
新聞記者らしく、終始走り続けたあっぱれな人生だったが、ポッカリ空いた喪失感はぬぐえない。8月はそういう人をまた思い出させる。パイプをプカリとふかそうか。