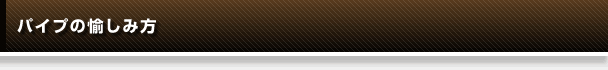パイプの愉しみ方
「50にして煙を知る」第34回 生涯一記者を体現した井上義啓さん
―ペンと紫煙、昭和プロレスの凄み―
 日本の春は別れと出会いの季節である。半月の間に卒業式、入学式と続く。学校の秋季入学が実現すれば、そういう意識も変わるのだろうか。
日本の春は別れと出会いの季節である。半月の間に卒業式、入学式と続く。学校の秋季入学が実現すれば、そういう意識も変わるのだろうか。
今年は遅い桜の花を見ながら、そんなことを思っても本欄をしばらく書いていない言い訳にはならない。昭和追憶ばかり続くが容赦願いたい。
熱狂的プロレスファンならば2006年に休刊した伝説のプロレス紙・「週刊ファイト」を知らない者は居まい。きっと野田佳彦首相も読んでいたはずである。
新大阪新聞社発行の同紙は、30年以上前、作家・村松友視氏の著書「私、プロレスの味方です」でも取り上げられ、一躍有名になったが、それ以前から、私も70年代末から80年代前半まで、熱烈な愛読者だった。
学生時代は後楽園ホール、蔵前国技館、日本武道館、品川プリンスホテル・ゴールドホール、大田区体育館、東京都体育館から、田園コロシアム、札幌・中島スポーツセンター、愛知県体育館まで足を延ばした。
80年夏、愛知県・一宮市立体育館でのハーリー・レイス対ミル・マスカラスのNWA世界ヘビー級選手権はしびれた。観に行ったんだな、これ。
署名入りプロレス社説
 「ファイト」は単に試合経過を追うだけではなく、その独特の視点、解説が読者を虜にしたのだ。
「ファイト」は単に試合経過を追うだけではなく、その独特の視点、解説が読者を虜にしたのだ。
とりわけ、67年創刊から93年まで同紙編集長を務めた井上義啓(いのうえ よしひろ)氏の署名入り社説「昨日 今日 明日 ファイト直言」「編集長 迷言集」を楽しみに毎週、高田馬場か池袋の駅売りで同紙を買い求めたものだった。
取材中、タイガー・ジェットシンに竹刀で突然襲われた際、「プロレスラーに粗暴さは必要か」などと大真面目に斬り込む文章など当時、どこにもなかった。
80年11月下旬だった。ラジオ報道の世界に入ってもう1年半だから、仕事はなんでも言い付けられた。76年カナダ・モントリオール五輪アマレス代表から新日本プロレス入りした大型新人・谷津嘉章(やつ よしあき)を、10分枠の短い時間ながら、インタビュー番組で取り上げた。
世田谷・野毛の新日本プロレス道場も覗きたい好奇心半分だったが、スポーツアナウンサーとのインタビュー応対がなかなか面白かった。
放送後、その時の録音テープ(当時、ラジオ番組はオープンリールテープで制作)を、カセットにダビングし、「ファイト」編集部に郵送した。
「関東ローカル放送だから、関西では聞けないし、編集長に聞いてもらいたいな」という井上ファンの素朴な気持ちからだ。
驚いたことに、2週間後に発売された同紙81年1月1日新年号に、その録音内容が大きく掲載されていた。「日程に手違いが生じ、渡米前の谷津に会えずじまい。あきらめていたら、YKさんから谷津のインタビュー・テープが送られてきた。番組で取り上げたそうだ。このご好意を無にしてはならない」とあり、インタビューの受け答えを紙面で再現しつつ、その数倍量の解説を付し、二面に渡る大記事になっていたのには仰天した。
それは紙面を無理やり埋めるためじゃなく、当時の谷津選手が取材するに充分値する存在だったからだ。「たった10分間のやりとりだけで、ここまでの記事になるのか。すごいな」と驚嘆した。一言100行、必殺仕事人の域である。
感激と恐縮で井上編集長に電話を入れたら、温和な声で「関西に来ることがあったら、ぜひ寄ってください」。うわ、これこそ出会いのチャンス!
黒半袖ワイシャツ、そして紫煙
その年の夏休み、関西旅行がてら井上さんを訪ねた。編集部に顔を出すと、井上さんは「や、どうも。ここは狭いしね」と仕事に打ち込む部員たちをちらっと目で示し、近所の喫茶店に誘われた。
私は27歳になったばかりだった。井上さんは47、8歳か、編集長として働き盛りだった。
神戸商大卒の、痩せ型で物静かな紳士だったが、そのスタイルは迫力充分だ。真夏にも関わらず黒の半そでワイシャツ(まあ、普通は着ません)にキリッとネクタイ、サングラス風メガネ(これも、なかなかすごい)、そしてゆっくり吸うが、タバコを絶やさない。すぅーと手がタバコの箱に伸びる様とタイミングが絶妙だ。
彼はホット、私はアイス珈琲を注文した。
「あのときはありがとうございました」から始まったが、あとは延々2時間、井上さんが話しづめで、それは力道山時代から馬場、猪木、鶴田、藤波(プロレスファンには説明不要です)に至るまで、彼が見聞きした四半世紀以上に及ぶ、ナマプロレス取材、体験談のオンパレードだった。野田さん、聞きたいだろうな、こういう話。
「この人もプロレス記者人生に賭けているな」と感じ入ったことと、黒の半袖ワイシャツ、タバコ(銘柄を覚えていないのは、私がシガレットを吸わないから)に火をつける独特のテンポだけは、はっきり覚えている。
おざなりにするな
数年前、「ファイト」が休刊したと聞き、もうプロレスを観なくなった私でも時代の変わり目を感じ、寂しかった。さらに時を置かず井上さんが死去し、追悼本が出たときはすぐ購入し、久しぶりにむさぼり読んだ。
後で知ったのは、彼は自宅に帰ることは稀で、会社近くに小さな部屋を借り、そこで寝泊りし、何かあればすぐ編集部に飛んでいったそうだ。やはり自腹を切る人は、どの世界でも強い。
活字の威力、「どうだ」といわんばかりの肉迫力は「ファイト」の筆致が教えてくれた。その影響は今も私の文体のどこかに内在している。
断片的な発言や表情から、レスラーの心理を察する井上さんの読み・解説は見事だった。いまでも50部ほど当時の「ファイト」を処分することができず、保存している。
 去年、「週刊ファイト スクープの裏側」なる本を見つけた。買って眺めていたら、休刊最終号に掲載された井上さん最後の原稿もあった。
去年、「週刊ファイト スクープの裏側」なる本を見つけた。買って眺めていたら、休刊最終号に掲載された井上さん最後の原稿もあった。
その一部を抜粋・引用させてもらう。
「人間、おざなりな仕事をしたのでは必ず悔いが残るものだ。その時は上手に立ち回って得をしたような気分になるものだが、時間が経つにつれて、それは苦い悔恨へと必ず変わる。
老齢の域に達して苦い思いを味わわされるか、満足だったと思うかは天と地ほども違う。人生とはそうしたものであろう」
「好きなことは24時間考えろ」が彼の哲学でもあった。
井上さんの人生には、戦争も、戦後の混乱も、阪神淡路大震災も全部呑み込んで生きてきた「昭和の生き証人」そのものの後姿が透けて見える。
存命だったら、3.11をどう表現したのだろう。
私もこの歳では、いまさら真面目に生きようとしても、もう遅い。馬齢を重ねるとは、よく言ったものだ。
井上さん、結局、一生怠け者で終わりそうです。