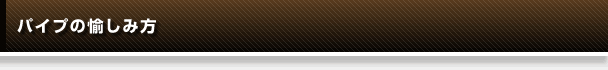パイプの愉しみ方
バレエ 素人鑑賞記

新国立劇場バレエ団(東京・初台)の2022/2023シーズンの白鳥の湖公演(2023年6月15日)を観劇した。
 オデット/オディールを演じたファーストソリストの柴山紗帆、ジークフリード王子のプリンシパル井澤駿の踊りと演技がそれぞれ素晴らしかった。さらに完璧で洗練された踊り手たち、一糸乱れぬコール・ド・バレエのダンサー。伝統を重んじながらも随所に工夫を凝らした振付、衣裳、舞台装置。完成度の極めて高い公演だった。なお今回のオデット/オディール役で絶讃を博した柴山紗帆は高い実力が評価され、公演翌々日の17日にプリンシパルに昇格した。おめでとう。心から祝福する。
オデット/オディールを演じたファーストソリストの柴山紗帆、ジークフリード王子のプリンシパル井澤駿の踊りと演技がそれぞれ素晴らしかった。さらに完璧で洗練された踊り手たち、一糸乱れぬコール・ド・バレエのダンサー。伝統を重んじながらも随所に工夫を凝らした振付、衣裳、舞台装置。完成度の極めて高い公演だった。なお今回のオデット/オディール役で絶讃を博した柴山紗帆は高い実力が評価され、公演翌々日の17日にプリンシパルに昇格した。おめでとう。心から祝福する。
私は内外の様々なバレエ団の公演で「白鳥の湖」を百数十回はゆうに観ている。海外の一流バレエ団に優るとも劣らない見事な出来だった。舞踊芸術監督の吉田都の力量に感心した。
日本のバレエ藝術の水準は既に世界の最高峰に立っているといえよう。これは褒め過ぎではないと自信を持って断言する。
愛煙家団体の日本パイプクラブ連盟のホームページに、クラシックバレエの記事が載るのはとんだ場違いと思われる方も多いだろうから、まず説明しておく。
パイプ愛煙家の中には本職の芸術家だけでなく、音楽や美術等々各方面の藝術愛好家の方が多くいらして、仲間内のパイプを燻らしながらの会話ではしばしば藝術論に花が咲く。クラシック音楽関係ではD氏、H氏、美術関係では K氏やS氏という具合に、鑑識眼を備えておられ、マスコミ等に載る浅薄な商業批評類とは一線を画した批評をなさる方がおられる。その識見の深さに学ぶところばかりだ。
私はそれら具眼の士には及びもつかぬが、素人ながら内外のバレエ公演には半世紀の間、足繁く通ってきている。パイプ仲間内の場で、ついバレエが好きだと口を滑らせてしまった。しばらくしたらパイプクラブ事務局の方がどこかで耳にされたようで、「バレエについて時々、何か書いて貰えませんか」と寄稿依頼があった。身の程は弁えているつもりだから「下手の横好きに過ぎませんから」とずっと固辞していたが、とうとう拝み倒されたという次第だ。
そこで初回となる今回はまず私のバレエ鑑賞遍歴も織り交ぜながら、日本のバレエについて思いつくままに振り返ってみたい。
 運動神経が鈍くバレエとは縁もゆかりもなかった私がバレエ藝術に関心を持ったのは、半世紀以上前の田舎の高校生の時に「ニジンスキーの手記 肉体と神」(市川雅訳)を読んだのがきっかけだ。たまたま書店で見つけ、当時、高校生にはなかなか手が出せない高価な本だったが、何故か無性に読みたくなり貯めていた小遣いをはたいて買った。今でも大切に私の蔵書の中にある。その頃、頭でっかちで超人思想のニーチェ哲学に嵌りかけていたのが、この本と出会ったきっかけだと思う。
運動神経が鈍くバレエとは縁もゆかりもなかった私がバレエ藝術に関心を持ったのは、半世紀以上前の田舎の高校生の時に「ニジンスキーの手記 肉体と神」(市川雅訳)を読んだのがきっかけだ。たまたま書店で見つけ、当時、高校生にはなかなか手が出せない高価な本だったが、何故か無性に読みたくなり貯めていた小遣いをはたいて買った。今でも大切に私の蔵書の中にある。その頃、頭でっかちで超人思想のニーチェ哲学に嵌りかけていたのが、この本と出会ったきっかけだと思う。
帝政ロシア期のポーランド系のヴァーツラフ・ニジンスキーという天才舞踊家にして20世紀バレエに革命を起こした振付師の手記を読み、人間の肉体による舞踊を通じて藝術表現するバレエに強烈な関心を持った。
とは言っても、田舎ではバレエ公演は皆無。本物のバレエ公演に接したのは大学生になって上京してからだ。大学一年生の時に松山バレエ団の公演を観劇した。演目はチャイコフスキー作曲の「白鳥の湖」だったと思う。十分楽しめたが何か物足りない感じだったことを記憶している。藝術至上主義の固定観念が災いしたのだろう。牧阿佐美バレヱ団、谷桃子バレエ団、東京バレエ団、スターダンサーズバレエ団などの公演にも次々に行った。演目は覚えていない。いずれも楽しんだが、私が勝手に頭の中で描いていた藝術表現のレベルに達していなかった。甘ったるい砂糖菓子みたいな舞台だった。
というのも1970年代当時の日本のバレエ団の水準は、総じて素人学芸会の延長線のようなものだったからだ。優れた踊り手は個々にいた。コール・ド・バレエの水準もまずまずだった。しかし全体にどこか幼稚だった。
森下洋子と清水哲太郎が海外のバレエコンクールで1位と3位になったばかりで、俄然世間の注目を集めていたが、振付、演出、舞台ともに全体にちゃちで、私が期待していた「舞踊と音楽の總合藝術」の域には程遠かった。その中でチャイコフスキーの舞踊音楽はまさに真の天才のみが到達できる極致であり、幼稚な舞台を補って余りあるものだった。私がバレエに魅力を感じ続けたのは、音楽の素晴らしさがあったからだ。
日本国内のバレエ団の公演からはしばらく足が遠ざかったが、海外の一流バレエ団がたまに来日すると欠かさず公演を観に行った。ソ連のボリショイバレエ、レニングラードバレエ、キエフバレエ、英国のロイヤル・バレエ、フランスのパリオペラ座バレエ、オーストリアのウィーン国立歌劇場バレエ、米国のアメリカンバレエシアター、西ドイツのシュツットガルトバレエ‥‥。
その中でも圧巻だったのが昭和50年のロイヤルバレエの「眠りの森の美女」。抜きん出たスターダンサーはいなかったが、全体に踊り手の水準は極めて高く、振付と演出が素晴らしかった。衣装も舞台装置も絢爛豪華。舞台全てが玄人芸であり、「これこそ才能と厳しい修行に裏打ちされたバレエ藝術の粋だ」と圧倒されたことを鮮明に覚えている。
海外バレエ団の来日公演はいずれもチケットは高額だった。良い席から飛ぶように売れていた。貧乏な私もなんとか頑張ってチケットを手に入れたものだった。
外国の一流バレエ団公演の観劇で目が肥えると、「では我が日本は」とどうしても思ってしまう。ところが嬉しいことに1980年代半ば頃になると、日本の様々なバレエ団の水準が急速に上がって行った。「学芸会の延長レベル」から一気に脱して、観て楽しめる水準になってきた。主役級の日本人女性ダンサーは格段にレベルアップし、世界の一流の次のレベル位には到達していたと思う。日本の舞踊界の先人の弛まぬ努力と研鑽の賜物である。この背景には日本の急激な経済成長の結果、社会全体が豊かになったことがあったのは言うまでもない。
何よりも顕著なのは優れた日本人男性ダンサーが増えたことだ。昭和の時代はバレエといえば「ハイカラな良家の女の子の習い事」と言うイメージが強く、男の子がバレエを習っているという話は聞いたことがなかった。その結果、バレエ団には数少ない男性の踊り手しかおらず、女性ダンサーばかりで演出せざるを得なかった。男女一組で踊る振付が望ましくても女性だけでごまかすしかない。
主役を踊れる優れた日本人女性ダンサーは増えたが、主役級を踊れる男性ダンサーは数える程。国内バレエ団の公演では、外国人の一流男性ダンサーを招聘したり、他の国内バレエ団の男性ダンサーを借りて何とか上演する例が少なくなかった。某バレエ団の公演を観に行ったら、別のバレエ団の男性ダンサーが主役で踊っていて怪訝に思ったことがよくあった。日本人の男性ダンサーが一気に増えたのは、1990年代に入ってからだと言う印象だ。
ただ1980年代になっても、日本のバレエがどうしても欧米の一流バレエに及ばなかったのが体型の違いだ。米のご飯を食べて畳の生活を長くしていた胴長短足の典型的な日本人体型は、やはりバレエではあまり映えない。日本人ダンサーは踊る技術では欧米人に追い付き追い越していても、見栄えでどうしても損と言うところがあった。1980年代になると日本人の男女のダンサーは世界に数あるコンクールで上位入賞の常連となった。
吉田都が英国サドラーズウェルズ・ロイヤル・バレエ団 のプリンシパルとなり、熊川哲也のような卓越した若手ダンサーがローザンヌで金賞を獲得し、英国ロイヤルバレエ団に東洋人として初めて入団して大活躍しても、体格差のハンディキャップはどうしても拭えなかった。
体格差、体型差がほぼ無くなったのは21世紀に入ってからだろう。食生活が洋風化し、畳から椅子の生活になってから日本人ダンサーの体型と体格は外国人ダンサーに引けを取らないどころか、むしろ優美さ、しなやかさの面で有利になった感がある。
昔の手足が短く、どことなくチンチクリンな印象が拭えなかった日本人ダンサーの踊りを知っている私のようなオールドバレエファンからすると、今の若い日本人ダンサーの優美な姿は眩く映り、隔世の感がある。地方の小都市でも子供向けのバレエ教室が増えている。これから日本のバレエ界は黄金時代を迎え、世界に冠たる存在になることは確約されていると言っても良い。いや既になっていると言うのが実感だ。
本格的なバレエ好きになると来日公演を待つのでは飽き足らなくなる。私は海外に行く度にモスクワのボリショイバレエやサンクトペテルブルクのマリンスキー劇場バレエ、パリオペラ座バレエ、オーストリア国立歌劇場バレエまで足を伸ばした。残念ながらまだ行っていないのは英国ロイヤルバレエ。生きているうちに早く行きたいと念願している。
本場のバレエ公演鑑賞でがっかりしたのが、パリオペラ座。日程の都合でクラシック作品は観られず、コンテンポラリーダンス(現代舞踊)の演目だった。曲はジョルジュ・ビゼーの「アルルの女」とあって期待したが、振付と前衛的な演出が酷く、呆れて途中退席した。名前はあえて言わないが、現代フランスの著名な振付師には何か勘違いしている看板倒れの人が多い。振付師の振り付け通りに踊らざるを得ないダンサーが気の毒だ。ついでに言えば現代の作曲家にバレエ音楽の傑作を期待しないこと。その理由はわざわざ指摘するまでもなかろう。
2020年春から続いたコロナ禍の3年間、海外バレエ団の来日公演は全くなくなり、日本のバレエ団の公演も数えるほど。この3年余り、昔のバレエ映画のD V D作品や誰かがYouTubeに投稿してくれたバレエ動画を観るしかなかった。
久しぶりに観た新国立劇場バレエ団の白鳥の湖が白眉の出来だったことに満足している。